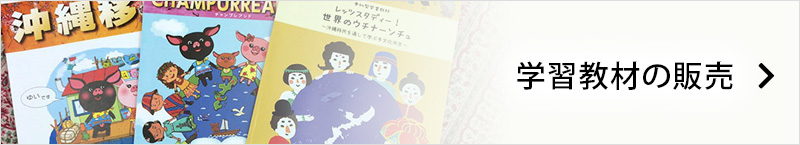こんにちは!
11月19日に、今回も沖縄大学でワークショップをしに行ってきました~!
前回は沖縄移民の歴史について勉強しましたね。沖縄移民は戦後、ハワイや南米等の多くの国に移住をしましたが、その繋がりというのは今では世界のウチナーンチュとして42万人の強い絆で結ばれています。びっくり!
そして、戦後の沖縄が食材や衣服等の物資が不足しているときに沖縄の人々を助けてくれたのがハワイに移住した沖縄の人々でした。前回の海豚ですね!そのため、私達が今食べている豚は沖縄移民の歴史を学ぶには必要不可欠なものですね。
では、私達が食べている豚や牛などの肉はどのようにして私達の食卓にやってくるのでしょうか?
今回のテーマは「食と命」です。
そのことについて学ぶため、今回は紙芝居になったタイにあるウムヨム村の豚のお話しと、沖縄大学の学生さんにより身近に感じてもらうために、宜野座村の農家の牛の話を通してみんなで勉強しました。
ウムヨム村ってどんなところなんでしょうか?
タイにある小さな村で、そこの村人達は沖縄の人々のように豚肉をよく食べています。けれども、スーパーで買うのではなく、自分達で育てた豚を自分達で仕留めて調理して食べています。普段スーパーでパックに入れて売られている光景をよく見る私達には衝撃ですよね?
紙芝居の最初に飛び込んできたのは丸焼きにされている豚の写真です。学生さんの中には「かわいそう…」という感想もありました。
けれども、ここで大切なのは「かわいそう」ではなく、「命を食していることへの感謝の気持ち」です。紙芝居を進めるなかで、ウムヨム村の村人達が自分達で育てた豚を食すのに祈りの儀式をしたり、その豚のことを忘れないように後には家に飾るなどをして大切にしている様子を見て、改めて命をいただくことのありがたさを実感しました。
そして、宜野座村の牛の話では、ONCスタッフ(さっさ~)の体験談を通して、食用とされる牛を育てている農家の背景や、その牛達を出荷するまでのいきさつについても勉強しました。
特に、食用とはいえ、生まれた時から愛情を注いで育てた牛を食べることって、簡単ではないと思う人も多いです。それは農家に務めている人々も同じです。けれども、だからこそ私達は食べ物を粗末にしてはいけませんよね。
授業を受けるなか、沖縄大学の学生さんも「食べ物への感謝を忘れたくない、と思った」や「食べ残しとかをなくしたい」といった感想を話してくれました。
私達は生きていく上で多くの命を糧として食していますが、感謝の気持ちを忘れてはいけませんよね。日本語の「いただきます」と「ごちそうさまでした」という言葉も、とても大切ですね。
次回のワークショップも学生さんと一緒に学んでいけるように頑張ります!